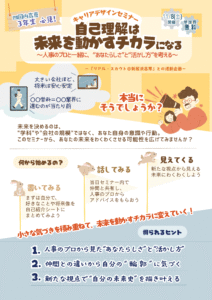高専には、全国の高専を対象としたイベントがいくつかあります。
今回は高専イベントの1つ、「高専デザコン」をご紹介します!
- 全国高等専門学校デザインコンペティション(通称:高専デザコン)とは
- コンテストについて
- <開催方式>
- <競技内容>
- 高専デザコンの特徴
- コンテストについて
- まとめ
全国高等専門学校デザインコンペティションとは
全国高等専門学校デザインコンペティション(通称:高専デザコン)は、
「人が生きる生活環境を構成するための総合的技術」として、デザイン力を競い合うコンテストのことです。
始まりは昭和52年まで遡り、明石高専と米子高専の建築学科で行われた
研究交流シンポジウムをきっかけとして、その後形態を変えて発展してきました。
近年ではCADや3Dプリンタを活用して行う「AMデザイン部門」が追加されるなど、
時代に合わせた進化を続けています。
コンテストについて
<開催方法>
年に一度、全国大会形式で行われます。参加チームの中から予選を通過したチームが、本選へ出場できます。
本選日程はその年によって異なりますが、概ね11月~12月に行われているようです。
また、本選の開催地は、全国の高専で行われます。
毎年、開催地が変わるのは、開催地域でものづくりや科学技術への関心を高めてもらうとともに、
高専生の技術の高さを示すことで、人材育成の成果を社会に示す機会となるためです。
<競技内容>
競技は、「①構造デザイン部門」、「②空間デザイン部門」、「③創造デザイン部門」、
「④AMデザイン部門」、「⑤プレデザコン部門」の5つに分かれて行われます。
毎年メインテーマが提示され、そのテーマに沿って各部門の部門テーマが設定されています。
ちなみに、令和7年度のメインテーマは『織りなす』です。
また、部門ごとに様式等が決められており、それらに沿った作品作りをして出来栄えを競います。
ここからは、各部門について紹介します。
①構造デザイン部門
紙等の材料を用いて橋や建物の模型を作り、その軽さや強度、デザイン性等の構造設計を競う部門。
②空間デザイン部門
建築分野のみならず、都市空間や土木構造物、
交通や情報空間等を含めた「人が生きる生活環境」という総合的な空間デザインの設計を競う部門。
③創造デザイン部門
地域社会の課題に対し、様々な視点からこれらの問題を解決する部門。
④AMデザイン部門
3次元CADや3Dプリンタを用いて新たなものづくりに挑戦する部門。
⑤プレデザコン部門
本科1年生~3年生を対象として、例年3つのフィールドが設定されている部門。
低学年対象ということもあり、比較的取り組みやすいテーマ設定となっていることが特徴。
高専デザコンの特徴
デザコンでは毎年、大会の全内容が収められたオフィシャルブックが発行されています。
各作品や全審査過程が収録された貴重な一冊となっています。
ネット販売もされていますので、デザコンが気になった方は購入してみるのもよいかも?
まとめ
デザコンは、高専コンテスト4選の中でもっとも歴史が古く、
時代に合わせて変化・発展してきました。競技課題は、生活環境に関連した内容が設定されており、
よりよい生活空間について考える力・提案力が身につけられる機会になります。
また、全国大会方式で開催されるため、各高専で培われた学力やデザイン力を注いだ作品に触れることができます。
そのため、他校の学生が披露した技術に刺激を受けることや
自身のものづくりに対するモチベーションアップにもつながるかもしれません。
この経験は技術者としての糧となり、今後の進学や就職の際にも役立つと思います。
ぜひ、興味のある部門に挑戦してみてください!